情報誌や新聞などの速読術・速読法
速読法を行うに当たっては、
「すべてを読破すべき読書」
「ある一部を必要とした読書」
「目的が曖昧な読書」
それぞれについて違った速読法が必要となってきます。
いろいろな速読法があるのですが、その中でも最も難しいと感じるのは、一番最後の
「目的が曖昧な読書」
の速読法ではないでしょうか。
では、具体的にはどのような本がその曖昧なものにあてはまるのでしょうか?
.jpg)
具体的には、情報誌といった類の本などがそれに該当すると考えられます。
総合的な情報を載せた本が一般的には情報誌と呼ばれていますね。
写真が多いのが特徴ですが、文章もそれなりにあるので、速読の範疇に入ると思っていいでしょう。
あるいは、もと一般的なのは新聞に関しても言えると思われますね。
新聞は本ではないと思われるかもしれませんが、速読の対象としてはまず入ってくる媒体になります。
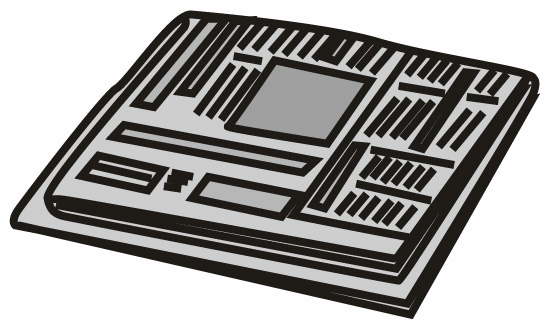
新聞についても、あなたにとって必要な内容かどうかがわからない状態で読んでいくのが一般的な読み方ではないかと思います。
こういった、目的が今一つ決まってなくて曖昧なものを読んでいく場合の速読法というのは、自分にとって本当に必要だと思われる情報を探すだけでも難しいものです。
また、逆に自分にはあまり必要のない情報と思っていても、実際に読んでみたら面白くてためになったという事も考えられるわけですので、最初を読んで簡単に捨てる事にも抵抗が出てきます。
そこで、最初の数行を読み、そこで判断するという能力がとても大事になってくるのです。
もし、最初の記事の数行を読んでみて、そこで今一つと判断したら、その時点で次の記事にうつるという感じで読んでいくのが、ベストだと思われます。
これにはちゃんとした理由があります。
それは、情報誌や新聞というのは、同じ人がすべての記事を書いているわけではないということです。

ですので、もし興味のない記事が続いても、別の記者が書いているものがあなたに向いている場合も考えられますので、その媒体(情報誌・新聞)全体を見切るというわけにはいかないのですね。
つまりは、記事単位で判断していくということになります。
それと並行して、最初の数行でその記事のポイントをある程度把握しなくてはなりません。
こういった情報誌や新聞などの情報発信を行う媒体は、読者に対して興味を引く為の仕掛けを書いてくることをよくやってます。
逆に言えば、そのギミックがない記事の場合、ライターがあまり考えて作っているわけではないという判断をすることもできます。
そんなちょと細かい部分も見逃さずに、記事が自分に合うどうかを常に判断していく癖をつけると、自ずと効率は上がってきます。
