読書での流し読みの是非
速読法を始めてしばらくすると、よくその技術について是非を問われることがあります。
その技術とは、、
そう、流し読みです。
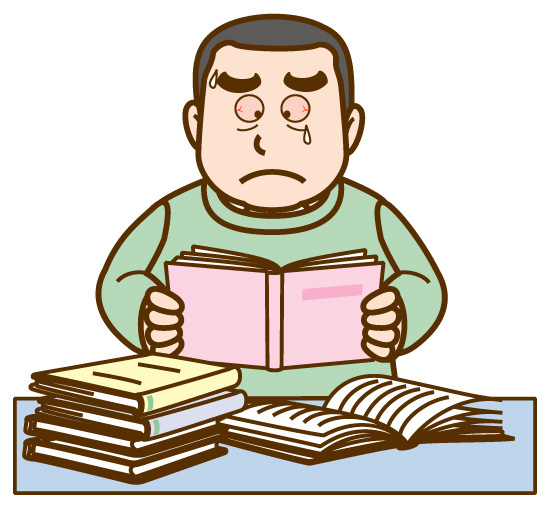
一般的に、流し読みに対しての印象はどちらかといいますと良いほうではありません。
なぜなら、流し読みをすることでは、内容をあまり理解できないばかりか、かえって時間の無駄と揶揄される事が多いからです。
では、速読法において実際流し読みは無駄な意味があまりない行為になるのでしょうか?
いいえ、答えは否です。
逆に速読法においての流し読みは、かなり大切だったりするのです。
ここでもう一度、流し読みを正確に見ていきましょう。
流し読みというのは、要するに本を素早くパラパラめくって拾い読みしていくというイメージですね。
拾い読みというように読みという語句が入っていますが、実際にはあまり内容は気にしません。
基本的なスタンスとしては、1ページにつきかける時間は1〜2秒で、さーっと流して読むという感じです。
そうなると、200ページの本を大体200秒〜300秒、つまり4、5分で読む計算になります。
しかし、ちょっと考えるとわりますが、1ページを2秒で読んだからといって、何かわかるのでしょうか?
流し読みの是非はまさにここがポイントで、流し読みの意味が大きく分かれるところでもあります。
しかし、流し読み肯定派では、その1〜2秒で判断できるものがあるから重要だと考えています。
具体的には、文体と文章の持つ雰囲気や項目を判断できると思うからです。
まず文体についてですが、物語を読む上で文体がどうなのかはとても大事なポイントです。
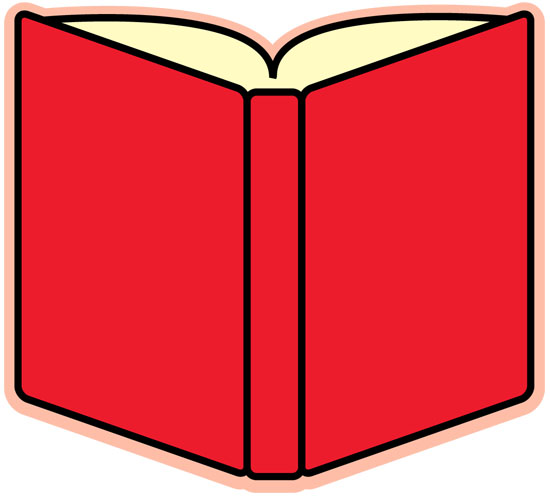
1人称で書いているのか2人称なのか、癖があるのか、堅いのか、稚拙ではないのか、などなどの判断は、1ページ1〜2秒でも十分にできることです。
次の、雰囲気ですが、これは正確に把握できなくても、その名の通りなんとなくの部分で感じる事ができます。
フィーリングが合うかどうかというちょっと別の次元の話かもしれません。
しかし、実生活も同じでフィーリングも結構重要です。
最後の項目に関しては、大体が専門書などの系統だった本の場合に考慮していく事になるでしょう。
目次だけを見るのではなく、実際にそのページを開いてみる事も大切なことです。
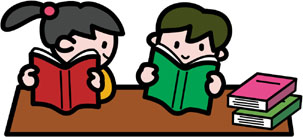
5分で、これらの様々なことを吟味するというのは、結構大切なのです。
なぜでしょうか?
それは、この事前の拾い読みの時点で、本格的に読むかどうかの見切りを付けられるからです。
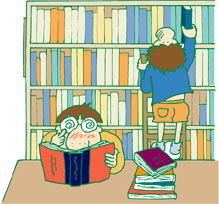
拾い読みの時点で、私にはあまり必要ない、あわないと判断できる本ならば、このたった5分で本屋さんの棚に戻す事ができます。
このように考えると、拾い読みもまた、速読のテクニックのひとつと考えることができるのです。
